
家族信託は、家族のいない単身者でも利用できます
この記事でわかること
- 家族信託は、家族に限定するものではないため、独身や子どもがいなくても利用できる
- 信託銀行や信託会社が提供する「商事信託」という方法もある
- 亡くなった後のさまざまな手続きのための「死後事務委任契約」という方法
家族信託とは、簡単にいえば「自分の財産を信頼できる家族などに託し、自分が決めた目的に沿って管理・運用を任せる」ことのできる仕組みです。例えば、自分が認知症になったり、寝たきりになったりして金銭の管理が難しくなる前に、財産を誰かに託しておくことで、万が一のときの日々の生活や通院、介護施設の費用などの支払いに備えることができます。
ところで、「家族信託」と聞くと、独身だったり、結婚していても子どもがいなかったりすると利用することができないのでは? と思ってしまう人は多いかもしれません。しかし、じつは家族信託は独身でも、子どもがいなくても利用できます。
家族以外でも「信じて」、「託す」ことは可能
信託とは、誰かを「信じて」自分の財産を「託す」制度のことです。そのため、家族以外の方でも信じて託す人がいるのでしたら、その方が未成年でない限り、財産を託すことができます。実際の活用ケースでは、託す相手が「家族」であることが多いため、一般的に「家族信託」と呼ばれているにすぎないのです。
例えば、自分は独身でも、頼れる身内として従兄妹やおい・めいがいるなら、その人に財産を託すことは可能です。あるいは、血縁関係がなくても、本当に信用できる相手でしたら、信託契約を結ぶことも可能です。

ただ、財産を託すことに決めた相手には、多くの権限が与えられると同時に、大きな責任が伴います。そして、受託者(財産を託される人のこと)は長期間に渡って、委託された財産を受益者(一般的には財産を託す委託者が受益者になる)の利益のため管理するという義務が生じるのです。そのため、受託者は本当に信頼できる相手にお願いすることが大切になってきます。
ちなみに、財産を信託する方法としては、商事信託というものもあります。商事信託では、信託銀行や信託会社が受託者になります。この商事信託は、信託の受託を業務として営利目的で行うため、受託者になるには国の認可(信託業の免許)が必要です。また、信託銀行や信託会社が受託する際には、当然ながら報酬が発生します。
一方、家族信託の受託者は大抵の場合身内ですので、受託者の報酬を無報酬としても問題ありませんし、事業としてやるわけではないので国の認可(信託業の免許)も必要ありません。
認知症になると財産が凍結されてしまう
自分が認知症になって判断力が低下すると、能力的にはもちろんのこと、法律上も金銭の管理が色々と制限されてしまいます。
例えば、認知症になって、ひとりで銀行の預金を引き出すことができなくなったとしても、親族などが代わりに引き出すことは原則としてできません。つまり、介護や医療にかかる費用や生活費を自分の財産から出すことができなくなってしまうのです。
また、本人の判断能力が著しく低下してしまうと、不動産の売買も法律上できなくなります。自宅を売って施設に入るなどが、難しくなってしまうのです。認知症の診断の有無に関わらず、本人の理解力が衰えてしまうと、遺言の作成や生前贈与などの相談対策もできなくなってしまいます。
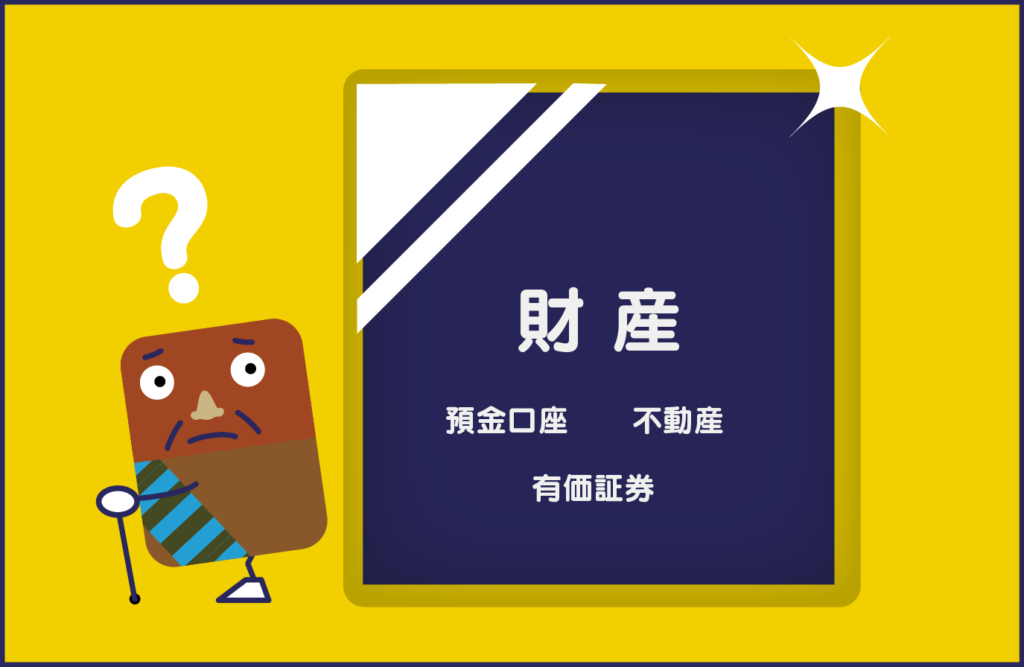
ですが、そうなる前に家族信託や商事信託などで、誰かに財産を託して、その管理を頼んでおけば、このような問題は回避できます。
認知症になる前の対策としてはほかにも、財産管理委任契約や任意後見制度もあります。財産管理委任契約とは、財産の管理に不安がある方(委任者)が身内の方や弁護士・司法書士等の法律専門職など(受任者)に対し、財産の管理に関する事務のすべてや一部についての代理権を与えるという制度です。任意後見制度は、本人に代わって財産などを管理してくれる後見人をあらかじめ決めておくという制度です。任意後見制度についての詳しい情報は、こちらの記事もご覧ください。なお、財産管理委任契約は本人の判断能力がしっかりしている間の制度ですので、判断能力が衰えた後は、任意後見制度に移行する、財産管理契約と任意後見契約をセットで契約することも良策でしょう。
亡くなったあとのさまざまな手続き
人が亡くなると、葬儀、火葬、埋葬、あるいは相続などに関して、さまざまな手続きが発生します。単身者の場合、それらの手続きは親族が行なうケースが大半ですが、労力的にも大変ですし、金銭的負担も小さくありません。そのような迷惑をかけたくないと考える人も多いでしょう。また、亡くなったあと、当人が生前望んでいた形で対処をしてくれるとも限りません。
そのような問題を解決する手段としては、死後事務委任契約というものもあります。これは、遺体の引き取り、葬儀や納骨・永代供養などの手続き、親族や知人への連絡、家賃や介護費用・医療費などの精算、行政の手続き、部屋などの清掃や家財の処分、Webサービスやデジタルデータの解約・処分、ペットの引き継ぎ先の指定などを、依頼者が生前に定めた受注者に託すことができるというものです。
死後事務委任契約で依頼できること
・遺体の引き取り
・葬儀や納骨・永代供養などの手続き
・親族や知人への連絡
・家賃や介護費用・医療費などの精算
・行政の手続き
・部屋などの清掃や家財の処分
・Webサービスやデジタルデータの解約・処分
・ペットの引き継ぎ先の指定
セットで包括的なケアが可能
ただ、死後事務委任契約では、財産に関する手続き(相続手続き)を依頼することはできません。相続分や相続人の指定といった財産に関する希望を実現させたい場合は、遺言書を残す必要があります。しかし、遺言執行は本人の意思に従った財産の継承を行うためのものですので、財産の継承以外の手続き、例えば亡くなったあとの親族や知人への連絡やペットの引き継ぎ先の指定などを依頼することはできません。
それらのすべての面をカバーしたいと思うならば、財産関係は「遺言」や「家族信託」、死後の手続き関係は「死後事務委任契約」という施策を組み合わせることが最適といえるでしょう。これにより各種手続きから財産の相続まであらゆる面で本人(依頼者)の希望を実現するとこができます。
もちろん、自分が認知症になったとき、あるいは亡くなったときの対策として何がベストなのかは、ご自身の希望や条件、状況によっても変わってきます。ソーシャルFPセンターでは、家族信託だけでなく、商事信託などもサポートしていすまので、一度ご相談ください。
